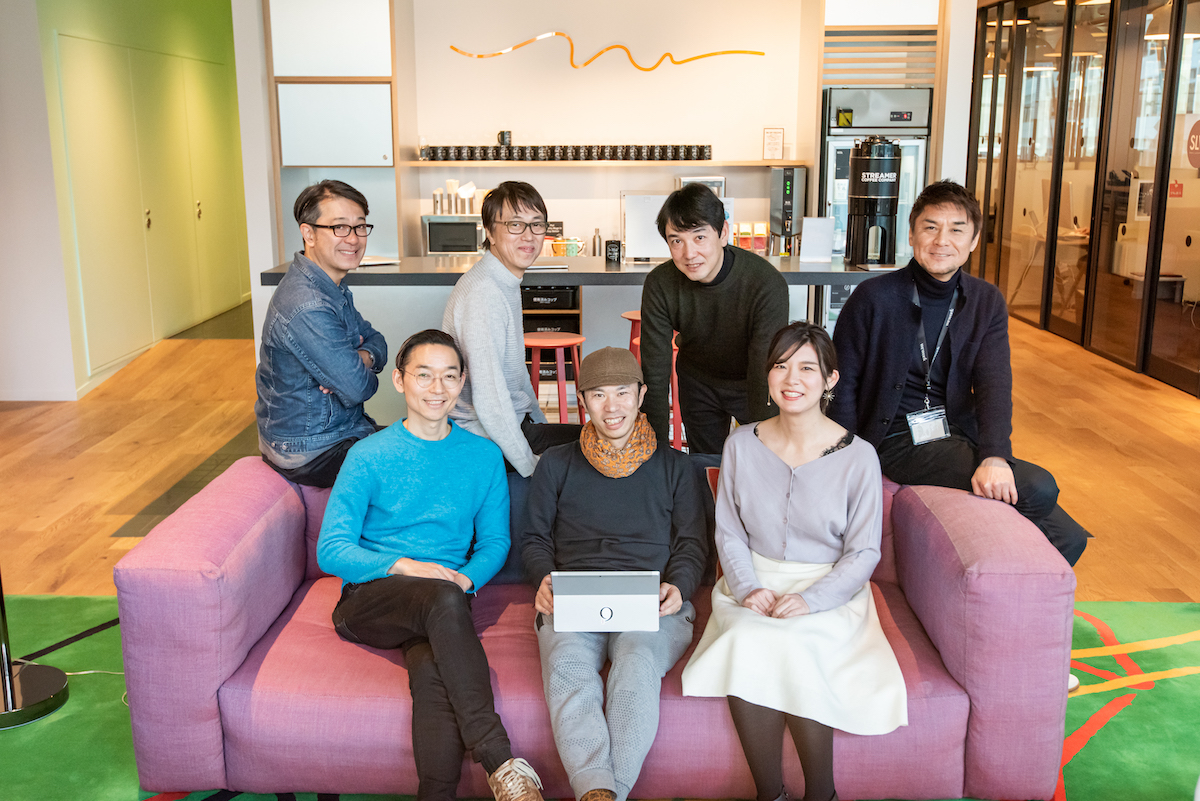みんなで悩みを聞いてみんなで解決する。集合知を形成する試み
仲良くなることが先。ビジネスはその延長線上にある
0→1部とコラボレーションしながら新規事業のテストマーケティングを行うPicassoプロジェクト
WeWork (ウィーワーク) では、入居メンバーが自発的に「部」を立ち上げ、精力的に活動しています。 WeWork アイスバーグ(原宿)で生まれた「0→1部(ゼロイチ部)」は、その代表例とも言えるでしょう。
同じライフワークや関心のあるテーマの下にメンバーが集まって活動し、公私を問わず助け合う中で信頼感を高めていく WeWork カルチャーをうまく体現し、ビジネス課題をも解決する「力」に変えています。今回は0→1部の発起人であるCUE代表(opportunity creator)の髙野一朗さんと、同部と新規事業のテストマーケティングを行うPicassoプロジェクトについてレポートします。
取材:Innovation Formula実行委員会(MGT田口雅典、稲垣 章)
みんなで悩みを聞いてみんなで解決する。集合知を形成する試み
— WeWork アイスバーグから生まれた部活「0→1部」とは、いったいどんな活動なのでしょうか
髙野氏:(以下、敬称略)私はアパレル会社でCRMを担当していましたが、その後独立し、マーケティングのコンサル業を営んでいました。もともと人と話をするのが好きで、人の相談は積極的に受けるタイプなのですが、かねてから感じていたのは、相談に乗る際のハードルの高さでした。
誰かの相談に乗るには、解決に行き当たらないとお互いの関係が微妙な感じになることがありますが、そのハードルの高さを取り払い、個々が持つ知を気軽に持ち寄り、大きな力に変えられるようにできたら、と考えていました。それが、0→1部発足のきっかけです。テーマと題目だけ決めておき、後はそこに人を集める機会をつくる——。それこそが問題解決に糸口になると考えています。
0→1部発起人のCUE代表の髙野一朗さん
— WeWork 内で部活にした理由はありますか?
髙野:企業に勤める人、あるいは私のような個人の入居者など、 WeWork には立場に関係なく多様な人が集まっています。誰かがその時に抱えているビジネスの課題、個人的な悩みなどを気軽にみんなで聞き、みんなで解決するのが0→1部の活動です。
WeWork には、そうしたビジネスに関わらずメンバーを助け合うカルチャーが存在していると感じたのが、大きな理由といえます。現在は、メンバー各々の関係性の中で、何か課題を抱えている人を見つけては、それをトピックとして会合が開かれています。
仲良くなることが先。ビジネスはその延長線上にある
—これまでの活動では、具体的にどのようなトピックが話し合われたのでしょうか
これまで4回の活動をしてきました。例えば3回目の会合では、メンバー企業であるDNP(大日本印刷)さんの新規事業担当者から「進行中のプロジェクトに対しての意見やアイデアを出すカジュアルなブレストをしたい」と、0→1部に相談がありました。
そのブレストの中では、DNPさんとビックカメラさんがコラボした「溶けない!?アイス」の販促イベントにつながるアイデアなどを話し合いました。また、Shopifyの「クライアントを増やしたい」という課題や、代官山の家具屋さんgreenicheの「 WeWork メンバーにお店のことをもっと知ってもらいたい」という課題にも取り組みました。
—ビジネス上の非公開なテーマもトピックとして話し合うことがあると聞きましたが、いかがでしょう?
髙野:すでに個々が信頼関係によってつながっているため、秘密保持契約のような堅苦しい契約文書を交わすフローをスキップして、スピード感を持って課題解決に動くことができます。DNPさんの案件についても、基本的には WeWork 内で信頼感をベースにしたオープンな環境の下で話し合いが行われました。
DNPさんを含む多くの入居企業には「 WeWork でのネットワーキングや対話から新しいビジネスを創出する」というミッションを持って入居しているところが多いですし、そうした堅苦しさのない環境だからこそ、柔軟な発想が生み出されると思います。
【事例インタビュー】大日本印刷が語る「WeWorkで創出するイノベーション」と「渋谷での新たな挑戦」
0→1部メンバーは、最初から何か大きなビジネスを生み出そうというより「この場所で何か一緒に楽しいことに関わりたい」というモチベーションで活動しています。仲良くなることで築かれる関係性が先で、ビジネスの話はその延長線上にあります。0→1部のトピックに上がったからといって「必ず結果を出します!」と約束するものではありません。その感覚を大切にしています。
─企業も個人も参加できる、その間口の広さこそが WeWork らしさですね
髙野:その通りです。参加しているメンバー間は、Slackで情報交換を行っているのですが、登録メンバーは現在40名ほどです。トピックによっては外部から有識者を招くこともありますし、 WeWork コミュニティチームを通じて会合を知り、飛び入りで参加してくれる人もいます。
0→1部とコラボレーションしながら新規事業のテストマーケティングを行うPicassoプロジェクト
髙野:直近の活動として、Picasso(ピカソ)という会議システムを使った実証実験があります。株式会社乃村工藝社、パナソニック株式会社、株式会社サカワから集まったメンバーで進めているPicassoのプロジェクトと0→1部とがコラボして進めているプロジェクトです。
─プロジェクトの詳細について教えてください
乃村工藝社 大河氏(以下、敬称略):発端は当社で進めてきた「究極の会議室」というプロジェクトでした。テーマは、徐々にオフィスやワークプレイスが発達していく中、いまだに進まないのが会議のイノベーションだと考えています。つまらないもの、面倒なものと敬遠されがちな会議を特別な時間へと変えるべく、パナソニックさんら複数の企業との共創でこのプロジェクトを推し進め、それを解決するプロトタイプとして「Picasso」を開発しました。
左からサカワの坂和寿忠さん、パナソニックの島田尚依さん、乃村工藝社の大河延年さん
—どのような経緯から0→1とコラボされたのでしょうか。
パナソニック・島田氏:こうした新規事業では、プロトタイプをつくり、その後展示会に出してフィードバックを得てブラッシュアップする、というサイクルがありますが、そのサイクルに陥ると、世の中にローンチできない場合もあります。今回0→1部と関わりを持ち、メンバーから率直な意見をもらうことで、世の中へ実装するフェーズへ一気に近づけるのではないか。そんな期待を持っています。
大河:プロトタイプをつくっても、それを試す場がないのが課題でした。そんな時、 WeWork コミュニティチームの皆さんから教えてもらったのが0→1部の存在です。そこでPicassoのフィードバックを得てみようということになり、2020年1月から約1カ月間、 WeWork アイスバーグの一室をPicassoの実証実験の場として使わせてもらうことになりました。
—実証実験の様子について教えてください
大河:Picassoには、標準装備としていくつかの機能を想定していますが、それをいくつか室内に設置して実際に0→1部のミーティングに活用してもらい、ニーズと改善点を共有いただきました。
株式会社サカワ・坂和氏:その機能として「発話の見える化システム」「アイディアアシスト」「時間管理タイマー」など、私たちが開発に携わったものもいくつかあります。もともと当社は創業100年の老舗黒板メーカーなのですが、近年は面白法人カヤックとの協業でハイブリッド黒板アプリ「Kocri」を開発するなど、アナログとデジタルの融合をテーマとした活動を行っています。今後はPicassoの機能をブラッシュアップして、実際に WeWork の会議室で使ってもらえるところまで高めていきたいと考えています。
—今後の0-1部の展望について教えてください
髙野:直近の話ですと WeWork メンバーが社内で受け持つプロダクトや個別に作られた製品を販売するECサイト”0→1部セレクトショップ”を、Shopifyさんを使って開設する案があります。
またWeWorkに入居されている新規事業担当者さんたちの日々の悩みや葛藤”あるある話”をまとめ、それを分かち合う座談会のようなものを現在企画中です!
***
このように、 WeWork では日々入居メンバー同士のコラボレーションが生まれています。業界業種を超えたコラボレーションに興味をお持ちの方、まずは是非 WeWork を体感しませんか? WeWork では、定期的に内覧ツアーを実施していますので、ご興味のある方はお気軽に WeWork へお問い合わせください!
[contact-cta link=”#application-contact”]お問い合わせはこちら[/contact-cta]